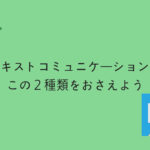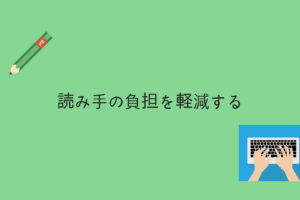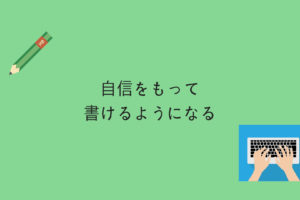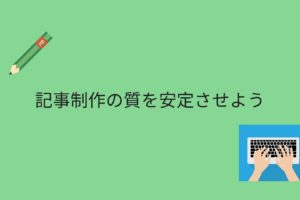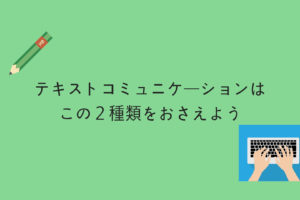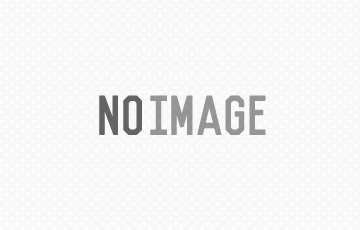文章力。何を指しているのか分かりそうでわからない言葉。現代はこの力がないとダメだ、と言わんばかりの強面で、ひとり歩きを始めている。危うい感じがする。
「文章力」と検索しても、出てくる記事はヒドイありさま。その中身について説明を試みようと挑んだものを見かけない。
という背景のもとに筆を執った次第でございます。若輩者ゆえご容赦を。
人はなぜ文章を書くのか
回りくどいですが、この問いから入らせてください(付き合ってるヒマはねえ、という諸兄姉は読み飛ばしてください)。人はなぜ文章を書くのか。
“人には「永遠でありたい」という願いがあるのだ”という、井上ひさしさんが『文章読本』で言う解釈。いまのところコレがしっくりきています。
せいぜい生きても七、八十年の、ちっぽけな生物ヒトが永遠でありたいと祈願して創りだしたものが、言語であり、その言語を整理し書きのこした文章であった。
わたしたちの読書行為の底には「過去とつながりたい」という願いがある。そして文章を綴ろうとするときには「未来へつながりたい」という想いがあるのである。|『文章読本』井上ひさし著 新潮文庫 p14
ぼく自身は「永遠でありたい」と願ったことはありません(笑)
しかし過去とつながりたい、未来へつながりたい、という表現ならば納得です。読書は過去とつながる行為、執筆は未来へと繋がろうとする行為。
「繋がろうとする」という点が大事。人はまだ見ぬ誰かとつながって生き永らえることを願う。多くの人がツイッターをしているのも、つながっている感じを確認したいからかもしれません。
文章力とは?
いよいよ本題。WEB巷の「文章力」とは少し異なる見方になると思います。結論をいえば「わからない」というのが正直なところ。文章力とは何を指すのでしょうか。
「文章を書く」という行為を細かく見ていくと、けっこう複雑なことをしています。
文章を書く力のことを文章力というが、では文章とは何か、それを構成する文字とは何か、言葉はどこからやってきたのか、これらの疑問について考えた上で、文字を綴っていく際に発揮される力の詳細に入る必要があります。
文字から入り、日本語の特徴や日本的感性についてギュッと凝縮して触れていきます。またこの記事より遥かに緻密で丁寧な書籍も紹介しますので、ぜひそれを手にとってみてほしいです。
***
漢字と東洋(的な世界観)の研究者である白川静さんによれば、文字には「呪能」というものがあるのだそうです。呪能という用語については、松岡正剛さんの著書『白川静 漢字の世界観』に以下のように説明されています。
呪能とは人間が文字に込めた原初のはたらきのことです。たいそう類感性に富んだはたらきです。またその文字が実際にもたらす意味の効能や作用のことです。文字呪能ともいいます。
呪能力とはいえ、呪うとは限らない。祝うこと、念じること、どこかへ行くこと、何かを探すこと、出来事が起こるだろうということ、それらを文字が、文字の力において、文字自身で果たそうとしているのが、文字呪能です。|『白川静 漢字の世界観』松岡正剛著 平凡社 p.35
人間が、文字に、何かの力を固定させようとした。その「何かの力」を総称して呪能と呼んでいると解釈しています。力を固定させるために文字が開発されたと考えれば、文字以前、つまり言葉(話し言葉)が呪能をもっていたといえます。
これに倣えば日本語にも呪能があります。日本は中国から漢字が運ばれるまでは文字をもたない社会でした。話し言葉のみで社会が成り立っていた。大野晋さんの『日本語練習帳』ではこの話し言葉をヤマトコトバと読んでいます。
古来の日本人が文字を使うようになったのは、中国から漢字を輸入してから。しかしそのまま用いるのではなく、もともと使っていたヤマトコトバの音と漢字の読みとを対応させるようにしました。
初めに万葉仮名という当て字のような方法を発明し、元々の意味内容が理解できてくると訓読みを当てるようにもなったそうです(借訓と呼ばれる方法ですが、まだ理解が腹落ちしていません)。
また書(行書や草書)の造形を仮名の開発に応用しました。漢字を崩した文字をひらがな(例:安→あ)に、漢字の部首をカタカナとして(例:伊→イ)、日本独自の文字体系を確立させました。
松岡正剛さんはこの流れも踏まえ、日本人は「歌」によって漢字を日本の国字として昇華させていったと説明しています。
まとめていえば、日本は「歌」によって国語を作ったのでした。いやいや、国語だけではないとも言いたい。今日、伝統文化とか和風文化と呼ばれている多くの日本文化の特質の大半が、ここから派生したというべきでしょう。|『白川静 漢字の世界観』松岡正剛著 平凡社 p.238
中国の漢字システムをまるまるインストールするのではなく、日本のヤマトコトバシステムに漢字の特徴(一文字で一つの音節、漢字によって音を表す)を取り入れて、全く新しいものをつくりあげた。
このハイブリッド感覚が日本的感性の源流なのだと思います。
***
人は言葉に何かの力を込めていたこと、文字にはそれを固定させる機能があること、漢字の渡来時の日本人がヤマトコトバシステムに漢字システムを上手に取り込んだことに触れました。
以上を踏まえると、文章を書く力の本来は「呪能を込める感覚が身体でわかること」にあると考えられます。そのためには文字を見て、原初の感覚まで時代を遡ってアクセスしていく察知力や想像力が求められます。
ちなみに白川静さんは文字をトレーシングペーパーで書き写しながら思考するという方法をとっていたそうです。目で造形を見て、手でカタチをなぞっていくことでその文字を扱っていた人と同じ身体の動きをしているのかもしれません。
文章の表現力についていえば、周辺環境の微妙な変化に応じて即興的に描写していく力が根底にあるように思います。例えば中国の書家、王羲之(おうぎし)の『蘭亭序(らんていじょ)』という作品。
新元号の「令和」は万葉集を参照元にしたと公表されていますが、蘭亭序が大元ではないかとも言われています。千六百と数十年前に、景色の良い郊外で詩を詠み合う会で即興で書かれたもの。あとでより良くしようと何度も書き直しても、最初のものを越えることはできなかったそうです。
千ウン百年もの歳月を経過してもなお残り続けるというのは、時間という問答無用の風化装置に抵抗しています。文章力というものは、”時間に抗う力”といえるかもしれません。
現代における文章力
先に挙げた内容は、文章力の普遍的な側面。それらを駆使している人はほんとうにひと握りだけ(ぼくも到底及びませんし、レベルの離れ具合もわからないくらいです)。WEBサイトやSNS上で言われている文章力は、こんな達人を指すものではないでしょう。
ニュース、取材記事、メール、ツイート、コラム、などを書く際に発揮される力。「ビジネスの文脈で語られている」と考えています。広く認知してもらい、顧客を獲得し、売上を積むための文章力。
その目的をひとまとめにすると「ウケること」で、内容は媒体に寄って微妙に変わります。以下、ぱっと浮かぶ媒体とそれぞれの評価指標を並べてみました。
プレスリリース…どれだけの媒体に紹介されたか
取材記事…PV、読了率
メール… 開封率、返信率、問い合わせ数
ツイート…RT、引用RT、いいね、プロフィールクリック→フォロー
ニュース、コラム、… PV、SNSでの拡散数(はPVに連動しますが
ブログ… 訪問数、読了率、指名検索数
「ウケたい」のは売上につながる(と思っている)から。その媒体が広告商品として成立するためには、基本的には閲覧数を増やす必要があります。
だからウケることを良しとして、ウケる文章 = いい文章 という図式ができあがります。但し戦略を間違えると「閲覧数は多いが成約にはつながりにくい記事」を量産することにもつながります。
欲する人に届くこと(さらには深く刺さること)がいちばん大事で、対面の場合と一緒だと思います。目の前の人が欲している情報を差し出すのが応対の基本。
ウケる文章 = いい文章 の図式はあまり好きではありませんが、ビジネスという文脈で考えるならこれが現在の最適解なのだろうとも思っています。
言葉づかいのレベルに関しても、読み手の求めるものを著しく下回っていなければ問題なく機能すると思います(ということは読み手の質が媒体の質を決めるのかもしれません)。
想定している読み手にウケようと思った場合に必要な力は、「情報収集力」と「企画力」、次に「構成編集力」。細かい言葉づかい云々よりは、読み手が欲している情報(ネタ)をかき集めること、それを記事の体裁にまとめることにウエイトが置かれます。
ウケるために最も重要なのは、企画ができうるだけの情報を集めること。次に読み手が喜びうる企画を考えること。取材やインタビューをする際は現場での情報収集力も要りますね(これは質問力といえそうです)。
構成編集のメインは、情報の提示順を決めること。読み手の興味関心やコンテキストの共有具合などを加味して、情報の取捨選択とオーダーを考えていきます(パッと見の綺麗さもたいへん重要ですが、デザイン領域は力量不足のため割愛させてください)。
***
言葉づかいの細かな部分を軽視しているわけではありません。文章力という表現からは想像しにくい要素が、大きなウエイトを占めているのが実際のトコロなのではないか。その背景にはビジネスの都合があるのではないか、という見解です。
まとめ
「人はなぜ文章を書くのか」という問いから入り、文字の本来と日本的感性に触れ、現代における文章力の内訳までを考察しました。
ギュギュっとまとめると
本来的な文章力|文字に込めた力を察知・想像する力、また即興的描写力
現代的な文章力|情報収集力・企画力・構成編集力
となります。
最後にこの記事を通して感じてもらいたかったことをお伝えします。それは「何を下敷きにして思考をしているのか」を問うてみること。
本来的な文章力については、「まず源流を見つめること」という視点を下敷きにして語っていきました。
現代的な文章力は「株主至上資本主義の影響を強く受けているだろう」と考えていたので、ビジネスの文脈で見えてきたことを書いています。
思考がガチャガチャになっているときは、何を下敷きにしているのかを見つめていくと解決することがあります。
文章のこと、文字のこと、日本語のこと、当記事が何かに気づくきっかけとなれば幸いです。
参考書籍
『文章読本』井上ひさし著 新潮文庫
『白川静 漢字の世界観』松岡正剛著 平凡社
『日本語練習帳』大野晋著 岩波新書